今年のゴールデンウィーク。世の中は10連休という人も多かったようだが、フリーランスという”自由の身”になったら連休というものの有難みは半減した。クライアントはみな休み。唯一のレギュラーアルバイト先である英語塾も休み。レジャーといってもどこも高くて混んでいる。例年のように実家に帰省?いや、10日間では長すぎる。働かなければ収入のない身なのであるから、いっそ連休期間限定のアルバイトをしようと考えた。
本業は基本的に書き仕事。取材時以外はじっとパソコンに向かう時間が長いため、アルバイトはデスクワーク以外がしたい。それもたくさん身体を動かす仕事ならエクササイズと一石二鳥!
などという甘い考えのもと、世の中が休んでいるとき最も忙しい場所、つまり観光地の宿泊施設で接客業(の裏方)というものに初挑戦したのである。
▲岩手のソメイヨシノはゴールデンウィークが満開。 お世話になったのは、岩手県のとある温泉旅館。一言でいえば、予想通り大変な仕事だったがやってよかった。何事も、実際に経験してみるまで分からないことはたくさんある。
一口に宿泊施設といっても規模や業態は様々だから、今回の私の経験が業界全体に当てはまるとは思わない。が、おそらく中小規模の温泉旅館というのはどこも似たようなものではないだろうか。世の中が10連休なら、彼らは10連続勤務である。その後に交代で10連休がとれるわけもない。しかも連日早朝から深夜まで(昼の中休みはあるにせよ)の長時間労働。その合間に10分程度で3食のまかないご飯をかきこむ生活だ。
仕事は配膳、清掃、洗い場、布団敷きなど。まさに私の望んだ「身体を使う」作業ではあったが、エクササイズを兼ねて、などというのは現場を知らない人間の思い上がりだと知る。念のため、と思って持っていった医療用コルセットが大活躍だった。私は短期の派遣バイトなのできっちり1日8時間しか働かなかったが、それでも最初の数日は終わるとぐったり。持ってきたパソコンをやっと開ける気になったのすら、5日目である。
▲バイト7日目、やっと少し余裕が出て中休みの間に行ってみた遊歩道 フリーランスになってから、いろいろな短期バイトをやってみた。収入の足しにという理由も多少はあるが、いちばんの動機は今まで経験したことのない仕事の世界を知りたいということだ。
2年前はキュウリ農家で週3日半4ヶ月のバイト (その時の話はこちら) 、昨年夏は桃の選果場で延べ1週間ほどバイト(その時の話はこちら) 。4月の桃の摘花やサクランボ授粉バイトは今年で3回目。そしてこの度の温泉旅館。その度に、それまで交わったことのないような人たちに出会った。5年前に福島に来て公務員になったとき、その時点で、あのまま東京で外資勤めをしていたら一生出会うことのなかっただろう人たちと知り合うことができたが、一次産業や接客業の現場は私にとって更なる「別世界」だ。世界は広い。
そして、こうした「身体を使う仕事」でいつも感じることだが、なぜこれら肉体的労働の対価は、いわゆる「頭脳労働」とされるデスクワークより相対的に低いのだろう。通常は「生み出す付加価値の違い」などと説明されるのだろうが、では彼らの生み出すおいしいキュウリや桃、そしておもてなしのサービスには、それだけの価値がないということなのか。どうしてもそうは思えない。
そもそも、こうした「肉体労働」に必要なのは体力だけで頭脳はいらないかといえば、そんなことはない。今回、旅館の食事で使われる膨大な種類の器の収納場所を覚えるだけでも大変だったが、なによりも、何を言い出すか分からない客のニーズに合わせて当意即妙の対応が求められる接客技術など、少なくとも私にとっては上級中の上級スキルのように思われる(幸い、私が直接応対する機会があったお客さんはみな常識的で優しい人ばかりだったが)。
みなが当たり前に期待する「日本のおもてなし」 は、 こうして3連休すら滅多にとれない現場の人たちの献身(ある意味犠牲)で成り立っているのだ。 日本のサービス業の労働生産性は低いというが、当然である。それが問題だという人は、いちど大型連休に旅館でバイトしてみたらよい。
▲自宅朝食の定番。食べたいときに食べたいものが食べられる贅沢。 農業やサービス業(コンビニも介護も含めて)の現場がいまや恒常的に人手不足なのは、周知の事実だ。「正当な対価」の考え方は人それぞれだろうが、なによりも足りないのはこれらの職業に対するリスペクトではないか。私は胸に手を当てて心からそう思う。リスペクトが欠けたまま、日本人がやらないなら外国人にやってもらおうというのでは、早晩おかしくなるだろう。
不特定多数の人が使うトイレの掃除とはこういうものか、なんてこともやってみて初めてわかった。駅にしても公共施設にしても、毎日こういう作業を黙々とやっている人がいる。 次にトイレ掃除の人を見かけたら「お世話さま」と言おう。 旅館に泊まったら、お布団敷いてくれる人には「ありがとう」と言おう。 いままでみたいに機械的にではなく、ちゃんと心を込めて言おう。
四半世紀以上、一人前に「仕事」というものをしてきたつもりで、初めてそんな当たり前のことをはっきり認識できた黄金週間でした。m(__)m
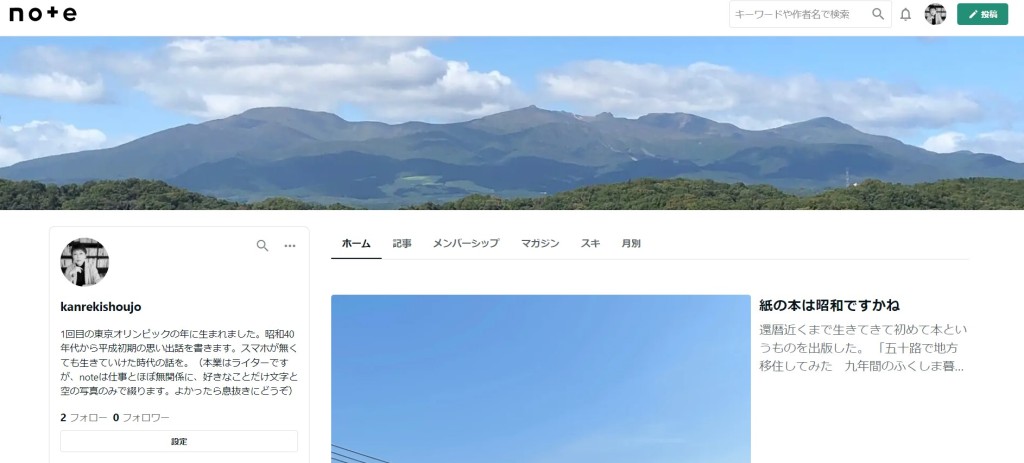
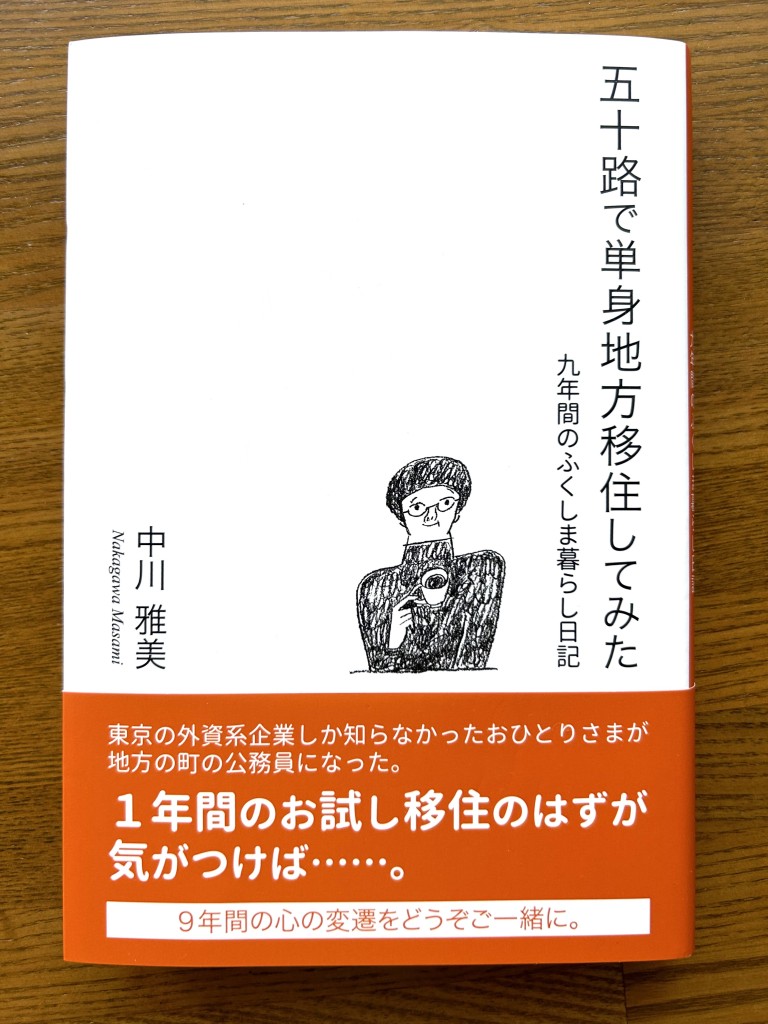
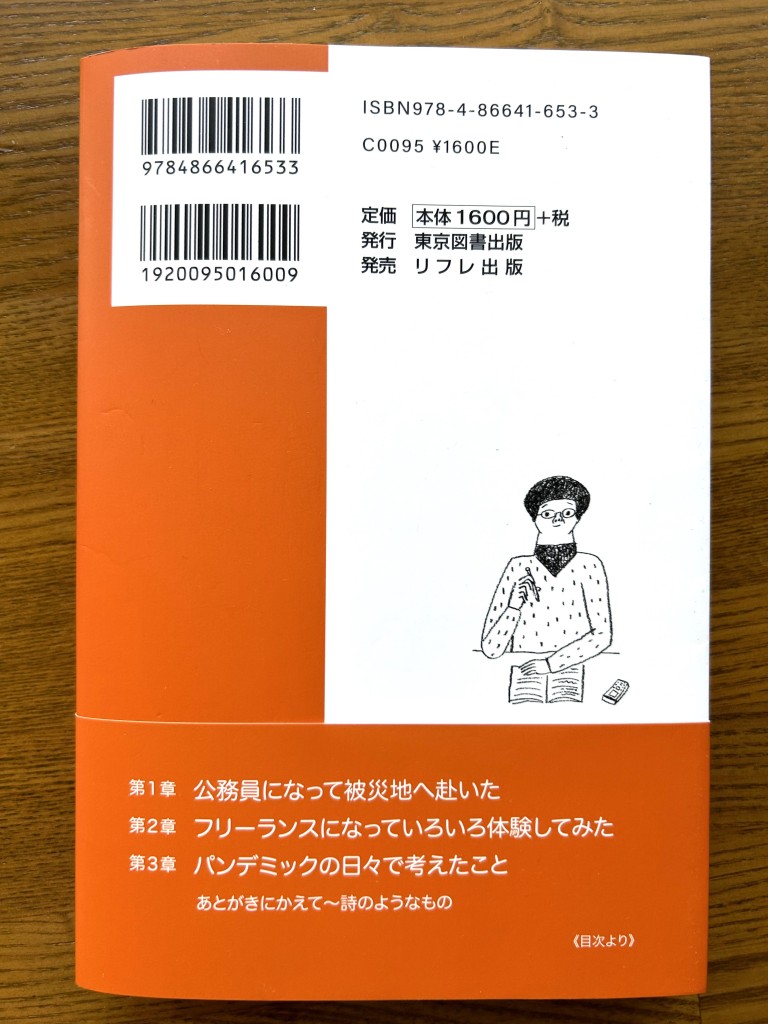





 心配した夕飯抜き(寺では正午以降は食べない)も意外につらくなく、かえって朝は身体がすぐ動くということも発見。そして、たった1日半だがスマホの電源を切ってプチ・デジタルデトックスできたのがよかった(したがって写真もない。芝桜の写真は、2日目の午後にみんなで散歩した芝桜公園でスタッフさんが撮ってくれたもの)。わずか2泊3日で何が変わったというわけではないが、なかなか興味深い体験ができ、誘ってくれたKさんには感謝である。
心配した夕飯抜き(寺では正午以降は食べない)も意外につらくなく、かえって朝は身体がすぐ動くということも発見。そして、たった1日半だがスマホの電源を切ってプチ・デジタルデトックスできたのがよかった(したがって写真もない。芝桜の写真は、2日目の午後にみんなで散歩した芝桜公園でスタッフさんが撮ってくれたもの)。わずか2泊3日で何が変わったというわけではないが、なかなか興味深い体験ができ、誘ってくれたKさんには感謝である。